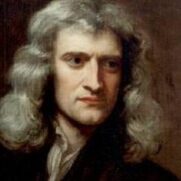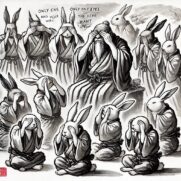もしあなたが完璧主義者でしたら・・・・・
以下長文ですが、完璧思考の罠について書いています。興味がありましたら読んでください。まずは自分の体験談からです、どうぞ!
「なぜ、私は動けなかったのか」——構造思考が教えてくれた本当の理由
私は長い間、完璧主義に縛られ、何かを始めようとしても、どこかで止まってしまう。その繰り返しにかなり苦しんできました。
「なぜ、動けないのか」「なぜ、手が止まるのか」——そんな問いを抱えたまま、時間だけが過ぎていく日々。
でも最近、”構造思考(特に緊張構造チャート)”を実践する中で、やっとその理由が腹落ちしたのです。
それは、「現状」と「理想」のギャップを見たとき、私は“埋められない不完全さ”に絶望していた、ということ。
完璧を目指すあまり、理想がどんどん肥大化し、現実との落差に飲み込まれていたんです。
その苦しみを「構造」として視覚化したとき、初めて、感情ではなく冷静な思考で向き合うことができました。
私たちが現場で成果を出すとき、
・どんな理想を描いているのか
・現実のどこに引っかかりがあるのか
・どの“緊張”が行動を止めているのか
これを構造的に捉えることで、「前に進むための問い」が立ち上がってくる。
私は、緊張構造チャートを通じて、”「行動を止めていたのは“自分の認知構造”だった」”という事実に向き合えました。
完璧主義は、悪ではない。ただし、構造として把握しなければ、私たちを動けなくする“静かなブレーキ”になります。
もし今、あなたが組織の中で「なぜチームが動かないのか」「なぜ私自身が迷っているのか」と感じているなら、それは、あなたの中にある“構造的な緊張”がまだ言語化されていないだけかもしれません。

☜完璧な会議(イメージ)

☜動き続ける会議(イメージ)
■「完璧思考」の罠に気づいていますか?
緊張構造チャートを前に、あなたはきっと真剣に、「何が本当に望んでいることか」「現状はどうなっているのか」を見極めようとされていますね。
このとき、注意すべき落とし穴があります。それが「完璧思考」という罠です。
完璧思考とは、なにか?
完璧思考とは、理想を描くと同時に、「現状はこうあるべきだった」「もっと整ってから始めるべきだ」「ちゃんと揃ってから動くべきだ」と、自分自身や状況に“完璧”を求めてしまう思考のクセです。
あなたの中で、こんな声が聞こえていませんか?
「まだ人が足りない」
「資金が揃ってから…」
「準備ができてから動こう」
「自分にはまだ力が足りない」
こうした声は、現実から目を背ける口実になります。
構造思考の支点は、「現実を直視する力」
ロバート・フリッツが構造思考で強調しているのは、「望む状態」と「現状」のギャップを、あるがままに見ることです。
ギャップがあるからこそ、創造のエネルギーが生まれる。
ギャップは失敗ではありません。原動力です。
完璧思考に陥ると、このギャップを「ダメだ」「情けない」と評価してしまい、創造の力を失います。
では、どうすれば完璧思考の罠に陥らずにいられるのか?
1. 評価ではなく観察せよ
「これはうまくいっていないからダメだ」ではなく、「今は、ここがこうなっている」と事実として見る。評価の癖を手放し、構造を観察する目を持つ。
2. あるがままの現実と、ありたい姿の両方を同時に抱えよ
「望み」と「現実」、どちらかに偏らず、両方をしっかり見つめること。これは感情的に苦しいかもしれません。けれど、その緊張こそが創造の源です。
3. 進む力は「完全さ」ではなく「方向性」から生まれる
完璧な計画も、準備も、必須ではありません。必要なのは、進みたい方向が明確であることです。歩幅は小さくていい。現実に働きかけることが、流れを生みます。
あなたは今、創造の起点に立っている
経営者として、理事として、地域のリーダーとして、あなたが向き合っている「望み」は、誰かの暮らしを支える力です。
だからこそ、完璧さに逃げず、未完成な現実としっかり向き合う姿勢が問われています。
「今、こうなんだな。でも、私は、こうありたいと思っている。」
この静かな宣言が、緊張構造チャートに命を吹き込み、現実に影響を与え始めます。
完璧ではなく、創造を。あなたが選ぶその一歩が、未来をつくっていきます。