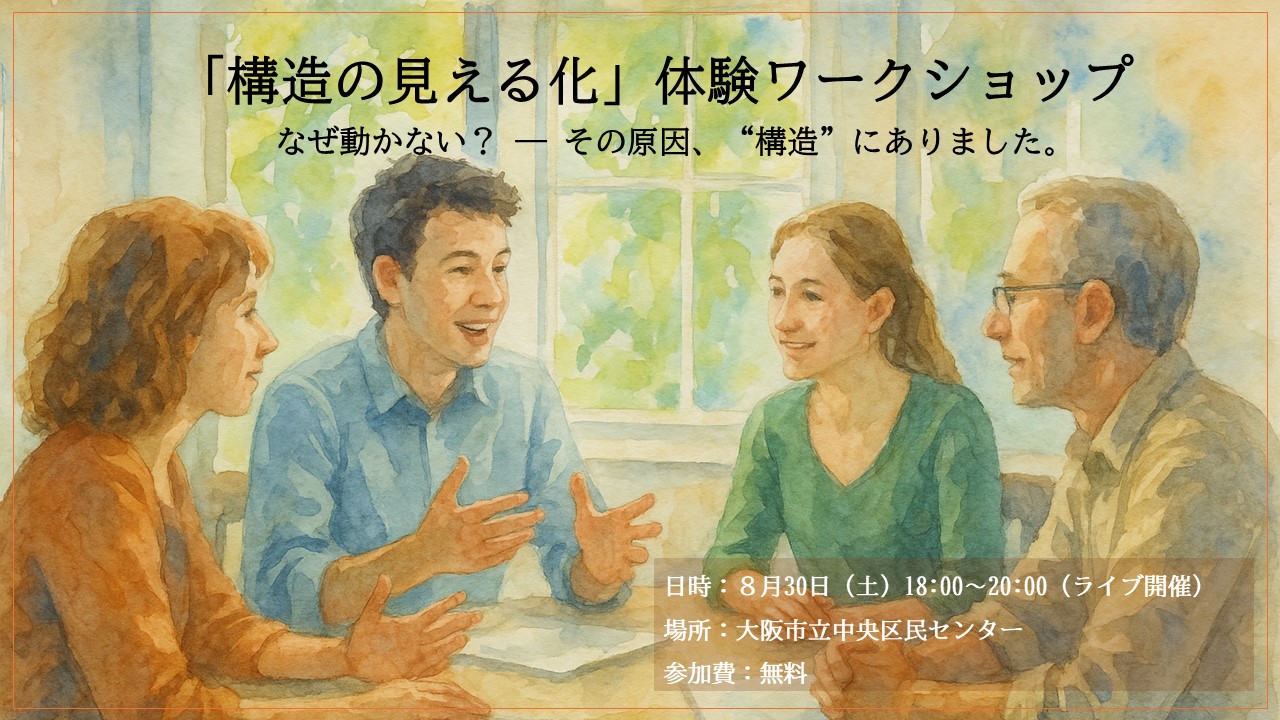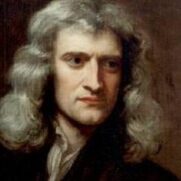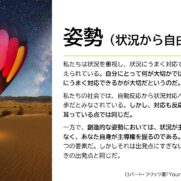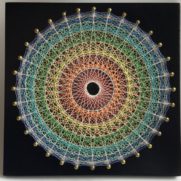- 地域の熱が冷めていくとき、そこに”構造”はあるか?
「とてもいい場だったんだけども、次が続かなくて」
「みんながんばっているのに、なんとなく空中分解しそうで・・・」
地域の循環共生圏づくりに取り組む中で、こんな声を聞いたことはありませんか?
実はこれ、”やる気”や”関係性”の問題ではなく
「構造がない」ことが原因である場合がほとんどです。
地域には想いのある人がたくさんいます。農、福祉、教育、エネルギー、環境、文化・・・・
それぞれの現場で、真剣に未来を考えている人たちがいます。でも、その想いがつながり、持続可能な仕組みになっていくには
「構造」が必要です。 たとえば - 誰が・いつ、何を決めるのか?
- 住民の声は、どこでどう拾われるのか?
- 単発イベントではなく、どうやって”続ける”のか? これらが設計されていないと、場の熱量に頼った一過性の活動になってしまいます。構造があると、地域は「続く・つながる・ひろがる」私たちFuture Creation Lab.オブリガードでは地域の想いや活動の”土台”を整えるために「構造の見える化」セッションを行っています。これは、頭の中にあるバラバラの想いを、緊張構造チャートという形で図にして整え、導線を引くプロセスです。たとえば
- イベント後の”次の一歩”が決まっていない
- 参加者がリピーターにならず、広がらない
- 自治体、企業、住民の連携が空中戦になっているそんな課題を、構造で整理していくことで、
「持続する地域のしくみ」がすこしずつ形になっていきます。あなたの“モヤモヤ”には、理由があります。
地域で活動を続ける中で、こんな声を聞いたことはありませんか?
「いつも同じ人ばかりが動いている気がする」
「何度も話し合っているのに、なかなか物事が決まらない」
「次の世代にどう引き継いでいけばいいかわからない」これらの悩みは、決して個人の努力不足ややる気の問題ではありません。私たちは、こうした停滞感の背景には「関係者の構造」があると考えています。
だからこそ、いま必要なのは
「関係性に依存せず、関係性が自然に育つ場づくり」です。
これは、地域における循環と共生を実現するための、核心となる視点です。
「構造」を見ることから、すべてが動き出す。
「構造」と聞くと難しく感じるかもしれません。でも、実際のセッションでは、とてもシンプルな問いから始まります。
・何が詰まっていると感じますか?
・誰と、どこで、何が止まっていますか?
・どこに“導線”がなくなっているでしょうか?図を描きながら、地域活動の現場を一緒に眺めていくと、「だから進まなかったのか」と、自然に見えてくるものがあります。これは、静かだけれど力強い場です。
このワークショップは、派手な演出も、正解の提示もありません。
けれども、そこには確かな想いがあります。・上手くいかなかった過去
・伝わらなかった言葉
・止まってしまった時間そうした現実を越えていくための鍵が、「構造を見ること」なのです。これは、人を責めたり変えようとする視点ではありません。
今ある“流れ”を見直し、もう一度、前に進む力を取り戻すための視点です。この小さな場で、「構造」と「希望」がつながる感覚を、ぜひ体験してみてください。
こんな方におすすめです
・地域活動が”想い頼み”で続かないと感じている
・イベント後の仕組みづくりや連携がうまくいっていない
・次世代へのバトンや、他分野とのつながりを模索している
- 「構造の見える化」体験ワークショップ
 開催概要日時:8月30日(土)18:00〜20:00会場:J:COM中央区民センター(大阪市立中央区民センター)参加費:無料定員:10名(先着順)
開催概要日時:8月30日(土)18:00〜20:00会場:J:COM中央区民センター(大阪市立中央区民センター)参加費:無料定員:10名(先着順) 詳細・お申込はこちら
詳細・お申込はこちら