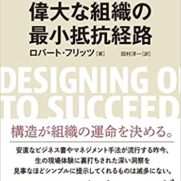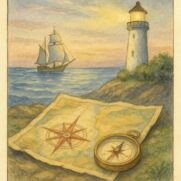緊張構造のアクションプラン 3つの特徴と価値
(3つの特徴)
1.ビジュアルでテンションを明確にする
チャート上で「現状」と「理想」を並べることで、目に見える形で緊張構造(テンション)を把握でき、何をすべきかが直感的に理解できます。
2.行動起点のアプローチ
構造アプローチは感情や抽象的な意欲論ではなく、「行動と結果」にフォーカスする実践的なツールです。日々の具体的行動が積み重なることで、現実の変化を確実に生み出します。
3.現場目線の柔軟な修正・更新が可能
状況に応じて計画や行動を見直せるため、環境変化や成果に合わせたリアルタイムの調整がしやすく、現場での実効性が高まります。
(3つの価値)
1.抽象的な理想を具体化する力
「売上を伸ばしたい」「組織を良くしたい」といった漠然とした理想を、現実的で明確なゴールへと落とし込む役割を果たします。これにより、目標達成に向けた道筋がクリアになります。
2.実行可能な一歩を設計する
チャートは、理想と現実の両方を認識し、二つの間にあるテンションの中で「今すぐ着手できる行動」を特定します。たとえば「今月中に10社に提案」や「2週間でリスト30件作成」といった、短期的・測定可能な行動を明確にします。
3.継続的な実行と進捗管理を支援する
単に計画を立てるだけでなく、週単位・月単位で実行状況を振り返り、状況に応じた修正を加える習慣づくりを促進します。これにより、アクションプランは常に「動く計画」として機能します。
この特徴と価値を、文化祭を例にあげて解説しますね。
文化祭でのクレープ屋さん出店の場合
あなたたちのクラスが「文化祭でクレープ屋を出す」とします。そのときにみんなで「文化祭でクラスの店を一番人気にしたい!」という目標を立てました。これが 「理想(ゴール)」 です。
でも、今の準備状況はこんな感じかもしれません。
・まだメニューが決まってない
・材料の買い出し担当も決まってない
・呼び込みの方法も考えていない
これが 「今の現実」 です。
じゃあ、どうする?
ここで 緊張構造チャート を使って、まずは「理想」と「現実」を確認します。
- 【理想】文化祭でクラスのクレープ屋を一番人気にする
- 【現実】準備がバラバラで、まだメニューも担当も未定
次に「行動」を決める!
みんなで「じゃあ、何からやる?」と考えます。
具体的な行動プランの例:
- 今週の金曜日までにメニュー3種類を決定する
- 来週の月曜日までに材料担当とレジ担当を決める
- チラシ作りチームを今週中に作り、配布用のデザインを完成させる
- 当日までに3回、クラス全員で試食会をして味の改善をする
このように 「いつまでに、何をやるか」 を細かく決めるのがポイントです。
なぜ役に立つの?
「人気店にしたい!」という理想だけを話しているだけでは、バタバタして時間切れになってしまうこともあります。でも、緊張構造チャートで「今の状態」と「必要な行動」を見える化することで、クラス全員が「じゃあ次はこれをやろう!」と一歩ずつ動けるようになるんです。
文化祭はチームプレーなので、「今、どこまで準備できているか」「理想に向かって、次に何をするか」をはっきりさせることで、みんなの動きがスムーズになります。
私たちは「文化祭で人気店にしたい!」というような、明るい大きな夢を語るのが好きです。でも、その夢だけを口にしていると、気づけば時間だけが過ぎてしまい、「どうすればいいのかわからないまま終わってしまった…」ということにもなりかねません。
でも、人は「今の自分」と「目指すところ」の間にどんな差があるのかを知ったとき、初めて、本当に行動する力が湧いてくるものです。そのために役立つのが緊張構造チャートです。このチャートがあると、「今、自分たちがここにいる」「だから次はこれをやろう」と、みんながはっきりと次の一歩を見つけられるようになります。
文化祭は、みんなで作る一つの舞台です。 各自が思いつきで動くのではなく、「今どこまで準備ができたか」「あと必要か」を全員で共有することで、チームは驚くほどスムーズに、力強く進んでいくのです。
文化祭だけではありません。このチャートは部活動でも、勉強でも、あなたの個人的な目標でも使えます。夢に向かって、一歩ずつ進むための地図のような存在です。
あなたも、自分の「今」と「理想」をつないでみたくなりませんか?